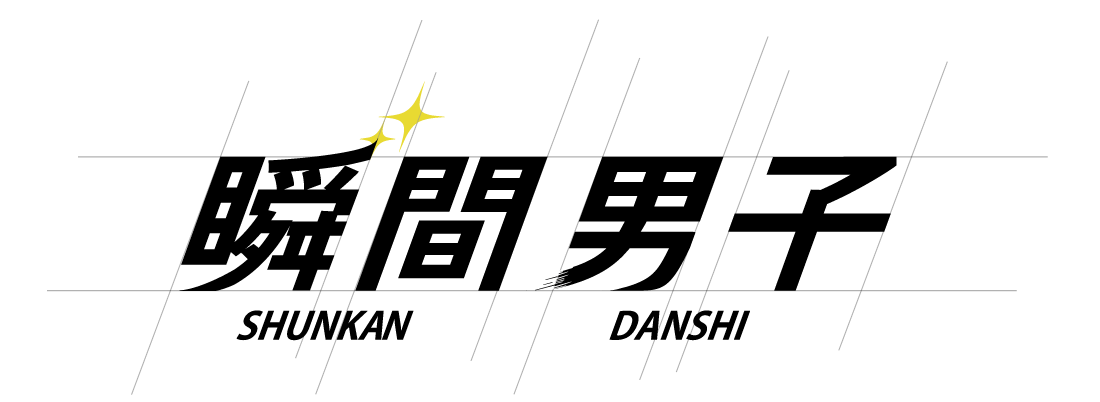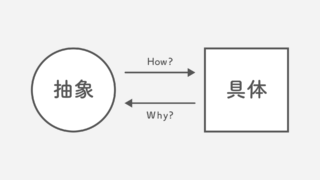「志望校が決まらない」「志望校の決め方を知りたい」という受験生向けの記事です。
この記事では、志望校の決め方や決まらない原因、決めるときに大事なことについて解説しています。
最後まで読めば「決まらない」と焦らなくなるはずです。
【結論】志望校の具体的な決め方
結論として下記のようなステップになります。
「志望校が決まらない」という受験生は以下の5ステップがおすすめだよ。
①将来どうしたいのか考える
②気になる学校の資料請求する
③全体的に資料を比較していく
④自分の未来にマッチする学校を3つ絞る
⑤徐々に本命の学校を決める「方向性を定め、情報を集め比較し、決断する」の流れが大事😇
— りっくん|瞬間男子 (@rikkunblog) October 24, 2019
ステップ①「将来どうしたいのか考える」
学校を決めるまえに大事な「将来」について考えましょう。
どんなことをして生きていきたいのか、やりたい仕事があるのかどうか。
人によって進みたい道が違うと思います。
やりたい仕事があるなら専門系の学校にいったほうが最短ですし、そうでないならそもそも進学をするのかを考える必要がありますよね。
ぼくの場合、「一緒に仕事をしたいひとを大学で探す」と決め大学進学することにしました。なので学校はどこでも関係なし。
自分がどうなりたいのか、なにをしたいのかを明確にしないと、大学の評価や周りの意見に流されてしまう可能性があります。
ステップ②「気になる学校の資料請求する」
将来について考え、「進学」という選択をしたなら、まずは学校の資料を集めましょう。
実際に学校にいって集めるのもいいですし、「スタディサプリ|進路」を使って一括で請求するのもいいでしょう。
だいたい10校の資料があるといいですね。
なんとなくで「○○にいきたい!」と決めてしまうんじゃなくて、最初は様々な学校を詳しく知っていく必要があります。
進学というのは少なからずお金がかかることなので、決断のまえの情報収集が大事です。
ステップ③「全体的に資料を比較していく」
資料が家に届いたら、全部一気にみて比較しましょう。
みるときは「判断基準」を決めておくといいですよ。
自分が大事にしている要素を決め、資料をみていきます。
「就職率はみなくていいの?」と聞かれそうですが、正直みなくていいですね。
そもそも学校側がだしている就職率が参考にならないこともありますし、なにより就職等は自分自身の能力が問われるので関係なし。
個人的には「学べること」を重点的にみてほしいです。
自分が興味のある分野を学べる学校にいけば、つねに知的好奇心を満たせて楽しい学生生活になること間違いありません。
ステップ④「自分の未来にマッチする学校を3つ絞る」
資料を全体的にみて「なんとなく良いな」と思うものを3つ決めましょう。
なぜ3つかというと、1つは絞りすぎだからですね。
もちろん「絶対○○にいきたい!」という強い意志があるなら問題ありません。
ですが、3つぐらいにしておいたほうが安心。
もし「○○学校」への熱が冷めてしまっても、志望校を「△△学校」に切り替えられるからです。
1つだけだとモチベーションが落ちたときに復帰しづらくなるので注意が必要ですね。
ステップ⑤「徐々に本命の学校を決める」
だいたい3つまで絞れたら、現時点で一番いきたい「本命学校」を決めましょう。
3つを徹底的に比較し、自分の未来に適した学校を選ぶのです。
本命が決まれば、必要な科目や学力、配点を把握したうえで勉強を進められて効率的ですよね。ぜひとも決めておきましょう。
【補足】3種類の志望校を決めておこう
3つまで学校を絞ろうといいましたが、補足しておくと「3種類」決めておくのも大事です。
具体的にいうと下記の3種類ですね。それぞれ「行ってもいいな」という学校を選ぶのがポイントです。
滑り止めは本命を落としたときのために。
ハイレベルというのは、本命よりもさらに難しい学校です。
3種類を定めておくことで、自分の成績の変動にあわせて修正が可能になります。
直前で「成績が足りないかも」と思ったら滑り止めに集中すればいいですし、想像より伸びたらハイレベルな学校に挑戦できます。
勉強前に志望校を3つ、3種類決めておくことで勉強していても「大丈夫かな」と不安になりません。
なぜなら成績がどう変化しても調整できるからですね。
志望校が決まらない原因は2つ
「なかなか志望校が決まりません…」と悩んでいる方は、だいたい下記の2つが原因かなと思います。
原因①「学校の雰囲気をみていない」
まず学校の雰囲気を知らないパターンがあります。
「高校/大学とは?」って感じ。
対策方法はシンプルに「学校に行ってみる」
実際に気になる学校に足を運んでみて見学しましょう。
学校のひとに要件を伝えたら通してくれる可能性があります。事前に電話しておくと安心ですね。
自分が通っている感覚で校内を歩くと「リアルなイメージ」が湧いてくると思います。
実際にいってみて「通ってみたいかも」という気持ちが生まれたら、志望校になりますよね。
原因②「知っている学校の種類が少ない」
志望校が定まらないひとに多いのが「知っている学校の種類が少ない」ですね。
そもそも認知している学校が少ない。
自分が住んでいる県の学校だけでなく、県外の学校にも視野を広げてみましょう。
それこそ「スタディサプリ|進路」をみれば、死ぬほど学校があるのがわかると思います。
といっても決まってなくても焦らなくていい
具体的な志望校の決め方を解説しましたが、決まらなくても焦る必要はありません。
悩む場合は時間をかけてじっくり決めましょう。
正直、志望校を決めることよりも「勉強」が大事です。あたりまえですが。
いつ志望校を決めても「このまま勉強するだけだ」と思えるような状態にするのがベストです。
学力や勉強姿勢が身についていれば、どんな志望校であっても対策できますからね。
【注意】志望校は必ず自分で決めよう
ここからはぼくからのメッセージです。
志望校を決めるときに「親に言われたから」「先生におすすめされたから」というのがよくある思います。
すべて無視して、ぜんぶ自分で決めましょう。
使いふるされた言葉でありますが、「自分の人生は、自分のもの」です。
どんな進路にして、どこでなにを学ぶのかは自分自身で決めたほうがいいですね。
他人に決められた道に進むのが正解かどうかなんてわかりませんが、後悔する可能性が高いのは間違いありません。
自分で決めたら「自分で決めたことだから」と前向きに捉えられますよね。
また、親の希望に従うことが「親のため」と思っているひとがいますが間違っています。
たしかに親に育ててもらった恩はありますが、親の希望に従う義務はありません。
親の最大の希望は「子供の幸せ」です。
親たちも勘違いしているかもしれませんが、子供自身が決めた進路で、それで子供が幸せならOKですよね。
大事なことなのでもう一度。
志望校は必ず自分で決めましょう。
【体験談】自分が志望校を決めたその後
ぼくが大学受験を決めたときの話をさせていただきます。
高3の4月に「大学に行く」と決めたと同時に『同志社大学』を目指すことを決めました。
ぼくのなかでは同志社しかみていなくて、徹底的に英語を勉強しました。
すると英語の偏差値が70、進研模試だと90とか意味がわからない数値まで伸びたんですよね。
結果的には「家賃が安いところに住みたい」という思いから大学を変更しました。今考えるとめっちゃバカすぎる。
といっても、大学進学の目的が「一緒に仕事をするひとを探す」だったので、まったく後悔していません。
大阪から京都に引っ越して、一人暮らしをするというのも、大学にいくというのも「すべて」自分一人で決めました。
そのかわり、学費や生活費は自分で払っていますが。逆境で成長しまくり。
もし、志望校を親や先生の意見で決めていたとしたら、めちゃくちゃ後悔していたと思います。
「自分で決めればよかった」って。
この記事を読んだ受験生のあなたも、必ず自分で決断しましょう。
若さゆえに判断を間違えることはあるかもしれません。
けど自分の人生を「自分で決めた」という経験は今後に活かされてくるはずです。
失敗しても取り返す精神も身につくしね。
ぼくの体験談が参考になれば幸いです。
ちなみに、体験談を受験生に向けて書いているので「受験勉強のすべてを詰め込んだ究極の完全マップ」もあわせてご覧ください。
おわりに「志望校も決めつつ勉強に集中しよう」
志望校を直感で選ぶのもいいのですが、正直資料を集めたり、実際にいってみたりするのがいいと思います。
判断材料は多ければ多いほど「選択肢」も増えますからね。
では、最後に記事で解説した「志望校を決める5ステップ」をおさらいしておきましょう。
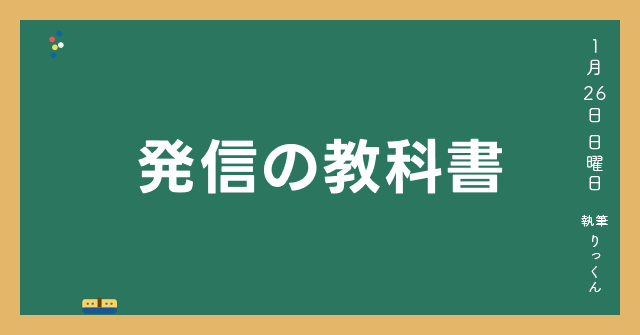
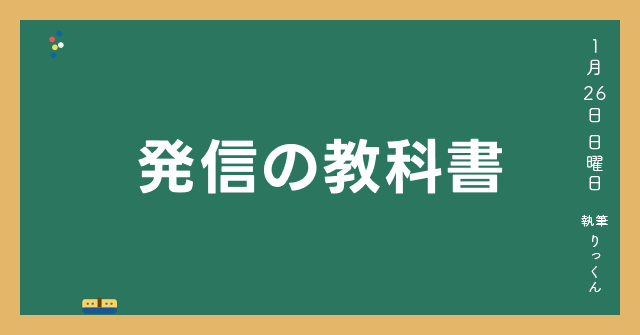
定価9980円の「発信の教科書」をタダでプレゼントいたします。
無料なのでサクッと受け取って、チャチャッと行動して、ポンッと結果だしちゃってください。
受け取りは下記のボタンからどうぞ。